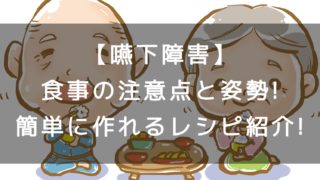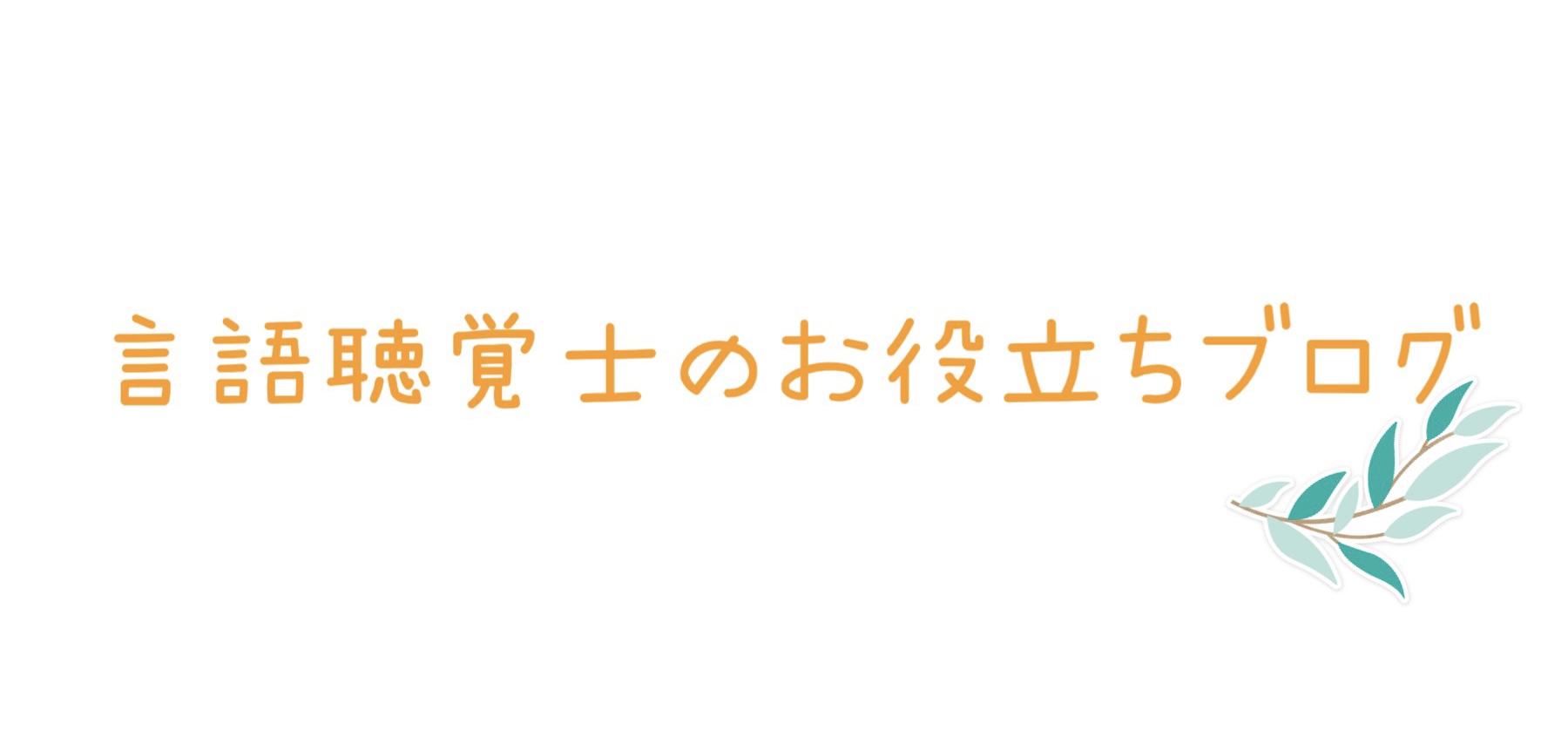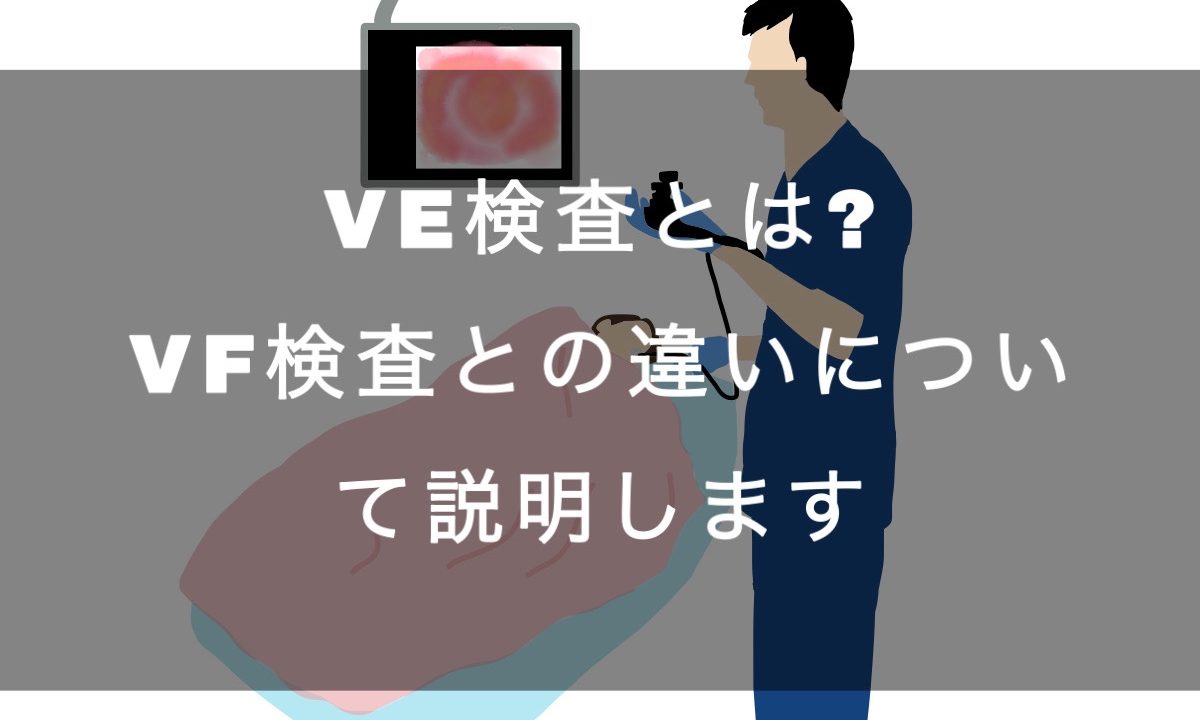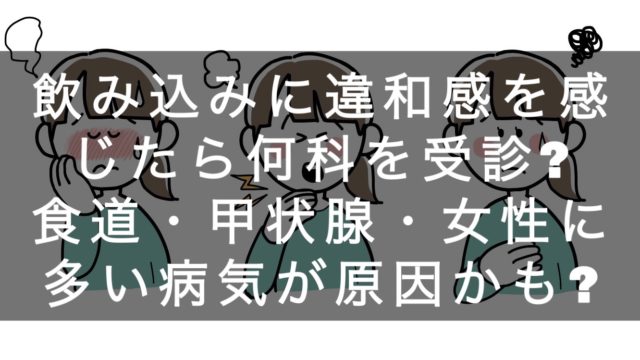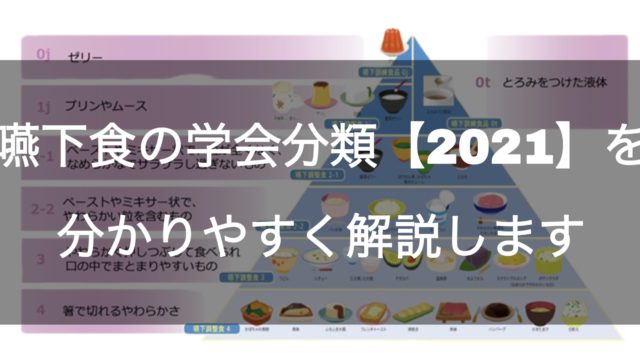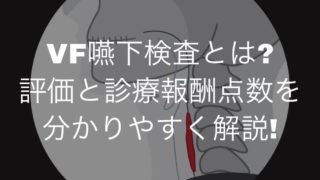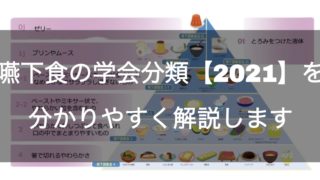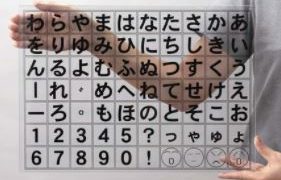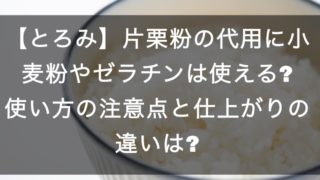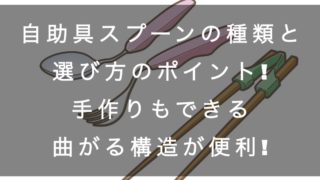今回は、VE検査とは?VF検査との違いについて説明します。
どちらも飲み込みの状態を評価する検査ですが、どんな検査なのか、それぞれを比較してメリット、デメリットを解説します!
では、はじめていきますね。
VE検査とは?
どんな機械を使用する?何をみる?
鼻腔ファイバースコープという内視鏡をのど(咽頭)に挿入し、食物の飲み込み(嚥下の様子)を観察する検査
唾液や喀痰の貯留の有無、食物を飲み込んだ後の咽頭内への食物の残留の有無や気管への流入(誤嚥:ごえん)などを評価することができます。
また、嚥下に影響を与えることのある声帯の動きも評価することができます。

検査の方法は?
鼻腔から内視鏡を挿入し、のどの状態を観察します。
【目的】
- トロミ付きの水、ゼリー、実際の食事などがどれくらい残るか、誤嚥はないかの観察
- 食物の摂取状況に応じて姿勢・食物形態・一口量の調整で上手に食べられるか試行錯誤する
【手順】
- 右か左の鼻から内視鏡カメラを挿入する
- 声帯・食道の入り口が見えたところで内視鏡カメラを固定し観察
- カメラを固定した状態でトロミ付きの水、ゼリー、実際の食事の順で
- どれくらい食物が残るか、誤嚥の有無を観察
- 咳払いや感覚などもみて、なんとか食べられる姿勢・方法を試す
【所要時間】
15分~30分程度
【実施場所】
ベッドサイド
VF検査との違いについて説明します
VE検査とVF検査の比較
高齢者の嚥下障害の評価とリハビリテーション 25巻8号 2016年8月15日 p.764-773より

VE検査のメリット
| 目的 | メリット | デメリット | |
| VF検査 | 造影剤(バリウム)を混ぜた食事をレントゲン下で写して、食べ物がきちんと食道に入っているかをみる。
どれくらい喉に残るのか。誤嚥しないで食べる方法の模索。 |
|
|
| VE検査 | 鼻腔ファイバースコープで実際の喉の状態、飲み込みの状態を観察する。
声帯の開閉や唾液の量などを直接見ることができる。 |
|
|
画像評価はなぜ重要?
- 嚥下運動は、外から視ることのできない運動のため
- 高齢者の嚥下障害では、咳のない誤嚥も多くみられるため
嚥下障害が疑われたら、VF(嚥下造影検査)やVE(嚥下内視鏡検査)にて嚥下動態(嚥下の一連の動き)を実際に目で見て評価することが、とても重要です。
誤嚥性肺炎を起こさないための管理、方法やその後の最良なリハビリテーション計画を立てるために欠かせない検査なのです。
新戦略はあるのか?
藤島先生たちは、嚥下CT による3 次元嚥下描出・解析や高解像度マノメトリーによる嚥下圧検査がある.いずれも嚥下の生理・病態理解および診断の精度を高め,嚥下訓練法の選択に有用なツールとして今後の活用が期待される.
としています。
今後、より負担が少なく根拠のある検査が開発されることに期待が持てますね(^-^ )
まとめ
今回は、VE検査とは?VF検査との違いについて説明しました。
どちらも飲み込みの状態を評価する検査ですが、どんな検査なのか、それぞれを比較してメリット、デメリットを解説しました!
どちらの検査も良し悪しがあります。しかし、検査しないと分からないことは多いです。
ぜひ、主治医の先生に相談してみてくださいね。