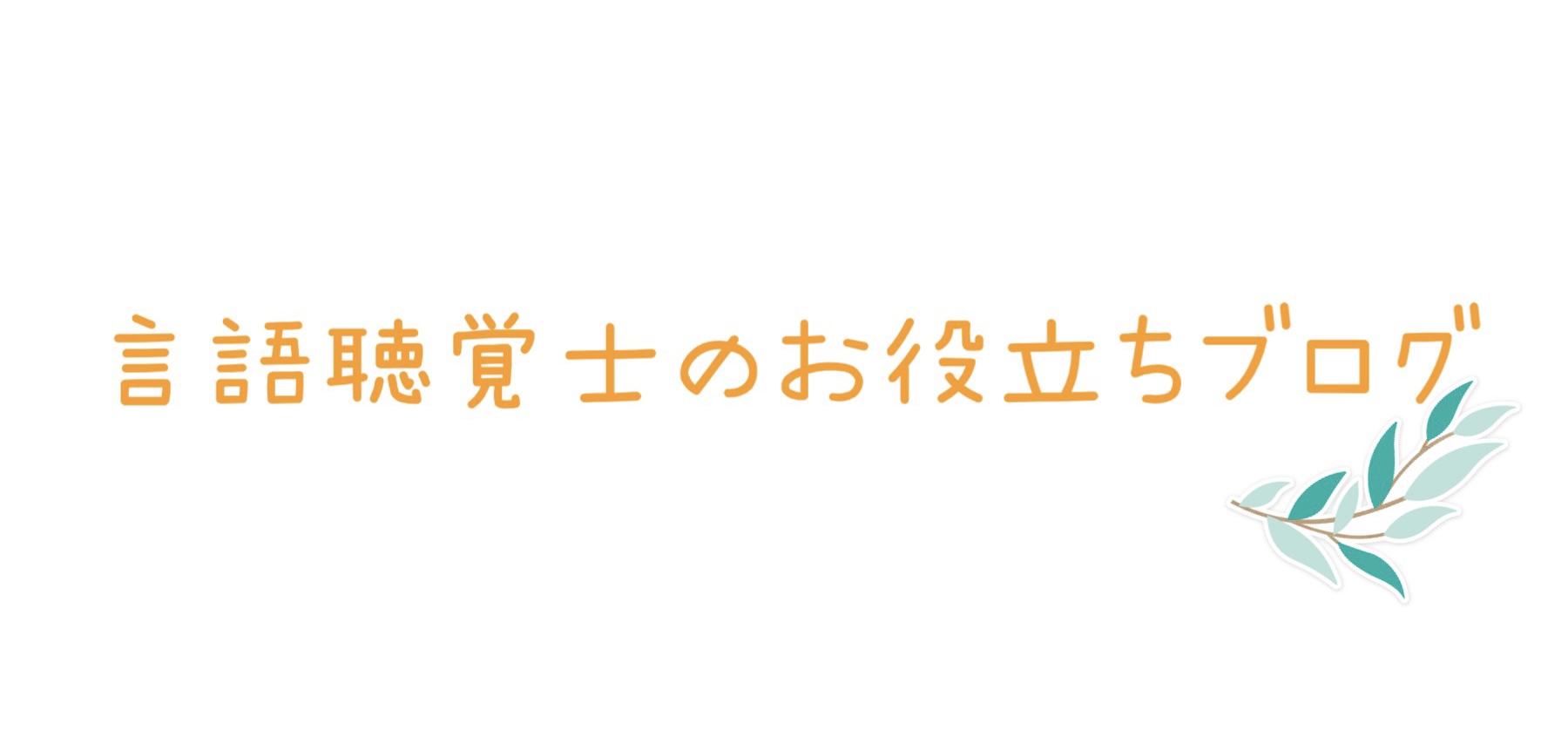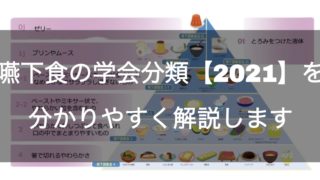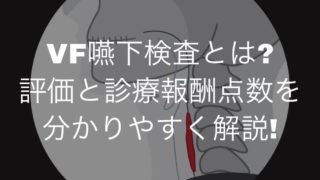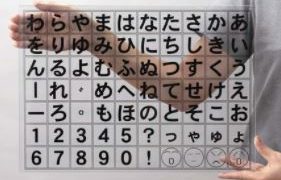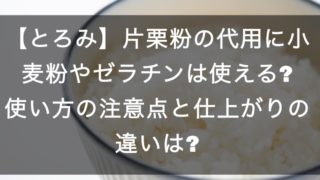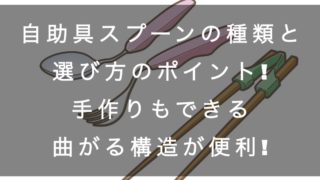今回は、高次脳機能障害と認知症の違いは何か、高次脳機能障害と認知症の併発しやすい仕組みや判断するポイントについてまとめました。
それぞれ、細かい種類の症状があり覚えるのが大変です。主な症状とまれに見られる症状などに分けて解説していきますね。
では、始めていきます。
高次脳機能障害と認知症の違いは?
高次脳機能障害とは?
脳は、外界から送られてくる様々な刺激をとらえ、言葉や動作に置き換えたり、学習したり、記憶します。
さらに記憶した知識や経験から判断をしたり、感じる(感情)、意志などの情緒機能もあります。こうした人間特有の高度な脳の働きを「高次脳機能」といいます。
「高次脳機能障害」とは、事故や病気などで脳が損傷されて、脳の精密な情報処理(高次脳機能)がうまくいかなくなった状態のことをいいます。
こちらの記事で詳しく解説しています!参考にしてみてくださいね(^-^ )
https://pressexpress.jp/gengotyouka-kaihukukikan/
高次脳機能障害の手帳申請の仕方は?等級や診断書についてまとめました

認知症とは?
認知症による「物忘れ」を「年のせい」だと思われている方が多いようです。しかし認知症は、年をとったことによる単なる「物忘れ」ではなく、治療が必要な病気です。
実際、80歳台の方4人のうち1人は認知症にかかっていることが分かっていますが、残りの3人は正常であり、高齢者と言えども、どちらかと言えば、正常者の方が多い、すなわち高齢になっても認知症にかからない人の方が多いのが現状です。
以下に、認知症の種類をまとめました。
- アルツハイマー型認知症(AD)
認知症のなかで最も多い疾患で、脳の変性や萎縮がゆっくりと進行します。海馬の萎縮により記憶障害が生じ、「物盗られ妄想」が特徴的です。
- 血管性認知症(VaD)
脳血管疾患によって引き起こされる認知症です。脳血管疾患の再発によって段階的に悪化していくため、生活習慣を見直して原疾患の再発を防ぐことが大切です。
- レビー小体型認知症(DLB)
神経細胞にレビー小体とよばれる特殊なタンパク質ができる疾患です。幻視、妄想、パーキンソニズムといった症状が特徴的です。
- 前頭側頭型認知症(FTD)
前頭葉と側頭葉が萎縮し、常同行動、社会性の欠如、脱抑制、感情鈍麻といった症状が目立ちます。
■認知症の方のうち50%はアルツハイマー病、20%が脳血管性認知症(脳梗塞などによるもの)、そしてレビー小体型認知症が20%と言われています。
それ以外に認知症の10%弱程度ですが、「治療可能な認知症」の場合があります。
例えば、甲状腺機能低下症、薬剤性認知症、ビタミン欠乏症、慢性硬膜下血腫、特発性正常圧水頭症などで、これらの病気は早期に発見しさえすれば、適切な治療により回復が期待できます。
きちんと検査を受けておかないと、治せる病気であるにもかかわらず、見逃されてしまうことにもなりかねません。きちんと診断することは、「治療可能な認知症」を見逃さないために非常に重要です。
違いについてのまとめ
認知症の人には、高次脳機能障害があるといっても間違いではありません。
なぜかというと、、認知症とは、アルツハイマー病や脳血管障害、ピック病など、さまざまな疾患が原因で記憶力や判断力が低下し、日常生活に支障が生じてしまったことで、症状や治療方法も多様だからです。
一方、高次脳機能障害は、厚生労働省の定義によると「事故や病気によって脳が損傷し、病気は治癒固定したものの社会に適応できない記憶や注意、遂行機能などの障害があること」です。
原因疾患は、脳血管障害、脳外傷などがありますが、アルツハイマー病などの進行性疾患は含まれていません。
つまり、脳卒中や脳外傷などが原因の認知症は高次脳機能障害ですが、アルツハイマー病などの進行性疾患が原因の認知症は、高次脳機能障害ではないと考えると良いでしょう。
認知症の原因の多くは、アルツハイマー病と脳血管性認知症です。
アルツハイマー病
- 脳の神経細胞が徐々に壊れてなくなっていく(進行性)。健忘を中心に始まり、徐々に認知機能が低下して日常生活に支障をきたします。
脳血管性認知症
- 脳梗塞などを繰り返すうちに、麻痺などに加え認知機能が低下していく。物忘れのほか、感情失禁(ちょっとしたことで泣いたり、怒ったり、笑ったりする)が見られます。
認知症と高次脳機能障害は後天的、つまりそれまでは健常だったのにある時期から認知機能の低下をきたす、という点については同じですが、もっとも大きな違いは、
認知症が一般的に認知機能が徐々に進行して行くのに対し、
高次脳機能障害は傷害を受けて障害となってから、回復する部分がある
ということです。
症状を的確に診断、対処すれば症状の改善が期待できるのです。
※症状に対する治療、リハビリテーションをしていく事が重要です。
高次脳機能障害と認知症の併発しやすい仕組みや判断するポイント!
併発しやすい仕組み
- 血管性認知症は高次脳機能障害としてとらえてよい。
- 血管性認知症は、再発がなければ、症状の進行は基本的にない。
しかし、年齢を重ねることで、徐々に脳血管が閉塞するようであれば、高次脳機能障害は悪化する
血管性認知症は高次脳機能障害!認知症は高齢になるにつれて発症しやすいが、高次脳機能障害も高齢になるにつれて血管が詰まりやすくなり発症しやすくなるため
参考:新潟リハビリテーション大学言語聴覚学専攻長・講師の佐藤厚先生
併発するというよりは、高次脳機能障害と認知症と間違えられやすいんですね。
認知症と高次脳機能障害の違い
- 認知症が比較的広く全般的な認知機能低下を生じ、多くは進行していく
- 高次脳機能障害は部分的な脳損傷で生じた特定の認知機能の障害であること
- 高次脳機能障害は、リハビリなどによってある程度の回復が望めること
判断するポイント
認知症は中核症状と行動・心理症状で見分ける!
まず、認知症の症状は、脳の障害により直接起こる症状である「中核症状(認知機能障害)」と、中核症状に付随して生じる症状である「行動・心理症状(BPSD;behavioral and psychological symptoms of dementia)」に分けられます。
図1中核症状と行動・心理症状(看護rooより)


認知症の中核症状の例として、次のようなものがあります。
もの忘れ(記憶障害)
- 数分前、数時間前の出来事をすぐ忘れる
- 同じことを何度も言う・聞く
- しまい忘れや置き忘れが増えて、いつも探し物をしている
- 約束を忘れる
- 昔から知っている物や人の名前が出てこない
- 同じものを何個も買ってくる
時間・場所がわからなくなる
- 日付や曜日がわからなくなる
- 慣れた道で迷うことがある
- 出来事の前後関係がわからなくなる
理解力・判断力が低下する
- 手続きや貯金の出し入れができなくなる
- 状況や説明が理解できなくなる、テレビ番組の内容が理解できなくなる
- 運転などのミスが多くなる
仕事や家事・趣味、身の回りのことができなくなる
- 仕事や家事・趣味の段取りが悪くなる、時間がかかるようになる
- 調理の味付けを間違える、掃除や洗濯がきちんとできなくなる
- 身だしなみを構わなくなる、季節に合った服装を選ぶことができなくなる
- 食べこぼしが増える
- 洗面や入浴の仕方がわからなくなる
- 失禁が増える
認知症に伴う行動・心理症状(BPSD)には、次のようなものがあります。
行動・心理症状(BPSD)
- 不安、一人になると怖がったり寂しがったりする
- 憂うつでふさぎこむ、何をするのも億劫がる、趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなる
- 怒りっぽくなる、イライラ、些細なことで腹を立てる
- 誰もいないのに、誰かがいると主張する(幻視)
- 自分のものを誰かに盗まれたと疑う(もの盗られ妄想)
- 目的を持って外出しても途中で忘れてしまい帰れなくなってしまう
高次脳機能障害は判断基準で見分ける
学術用語としては、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、この中にはいわゆる巣症状としての失語・失行・失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが含まれます。
【診断基準】
1.脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されていること。
2.日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害であること。
その他にも、高次脳機能障害であると診断される条件があります。
- 検査所見 MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できること。
高次脳機能障害に当てはまらない場合がある!↓
- 原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害以外の時
- 受傷または発症以前から症状がみられたり、検査所見を認める場合
- 先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする時
①高次脳機能障害は脳損傷の時期が明らかである。
②高次脳機能障害そのものは進行性の障害ではない。
まとめ
今回は、高次脳機能障害と認知症の違いは何か、高次脳機能障害と認知症の併発しやすい仕組みや判断するポイントについてまとめました。
それぞれ、細かい種類の症状があり覚えるのが大変です。主な症状とまれに見られる症状などに分けて解説してきたので、ポイントを絞って覚えてみてくださいね。
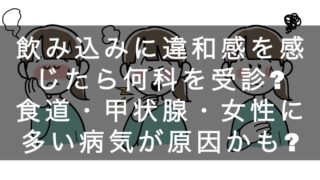
飲み込みに違和感を感じたら何科を受診?食道・甲状腺・女性に多い病気が原因かも?